2024年2月2日~4月21日に、SANOMAGICでは、二台目のランドナーとなる
マホガニーバイク39号機を制作しました。
ランドナーは、ロードバイクと異なり、泥よけとなる前後フェンダーを有し、
金具も多く、特殊な形状となります。
大変な手間がかかる分、できばえは素晴らしいものとなりました。
前後二回に分けて、レポートしましょう。
 |
マホガニー薄板。
各部の名称が書いてあるので、どれが何になるのか、制作工程を想像してみてください。
 |
これだけ幅広の積層体にするのは、シートステーが両側に開くためです。
 |
2つの型の間で、30枚ほどのマホガニー薄板を曲げて接合します。
極めて強い応力が閉じ込められ、それにより、フロントフォークの剛性が高まります。
 |
デ・キリコの絵のようでもあります。
 |
SANOMAGICマホガニーバイクでは、シートチューブとシートポストが一体となっています。
 |
サドルもマホガニー積層体で形成されます。
堅そうに見えますが、座ってみるとお尻に優しい不思議なサドル。
バイクを構成するすべてのパーツが衝撃を吸収するためです。
 |
ランドナーは他にも金具が多くて大変だったとのこと。
一台、一台、フレーム形状に合わせて異なる形状を削り出します。
 |
一つ作っただけで疲れそうだ。(-_-;)
 |
特に、フロントフォークとステアリングコラムの連結箇所には大きな力がかかるため、
末四郎が作るマホガニー積層体しか耐えられないでしょう。
 |
 |
トップチューブとダウンチューブの形になる。
両側の部分は、もったいないが破棄することになる。
 |
中空箇所は、別に作ったマホガニー積層体の蓋で塞ぐ。
中空部分の肉厚は、6mmとなります。
 |
 |
さらに、ステアリングコラムを挿入するためのヘッドチューブ部分を接合する。
 |
 |
マキハダは、槇の樹皮であり、木造船の建造になくてはならないもの。
船体外面を作る外板の間に詰めて水漏れを防ぎます。
マキハダが水分で膨らみ、外板の隙間を埋めることによる。
マホガニーバイクでは、トップチューブと、シートポストとを僅かな柔構造で接合している。
 |
この自転車は39号、次はとうとう40号となる(T号機は試作機のため含まず)。
一台ごとに洗練され、39号機は現在の頂点にあります。
 |
再びマホガニー薄板を切り出すところから始める。
 |
 |
タイヤの外周面にできるだけ近づけ、格好良く見えるように。
 |
 |
スポーク固定用の金具を一定間隔ごとに固定する。
 |
フレームに取り付けていきます。
 |
ここもマホガニー積層体で作ります。
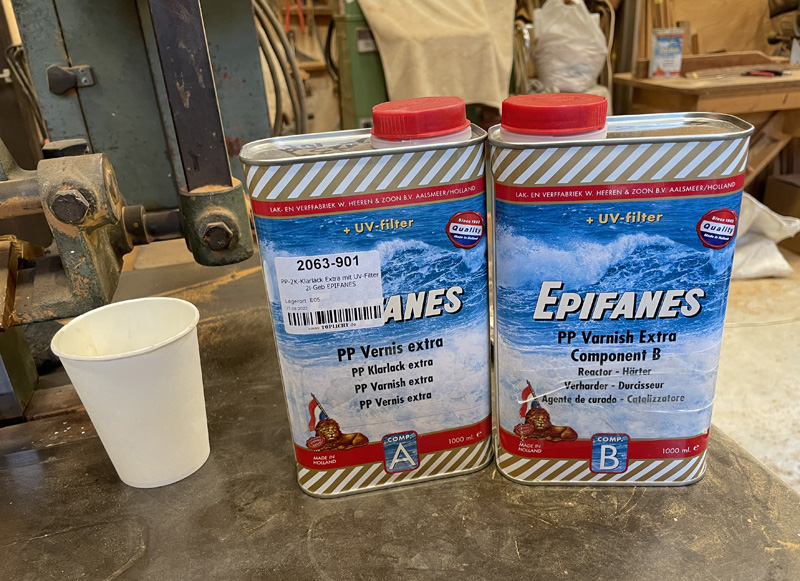 |
元々は、木造ヨットの製造に使用していた。
数十年、海水に浸かっても大丈夫な品質です。
以後のランドナー制作工程と試運転は、後半でレポートします。
乞うご期待。